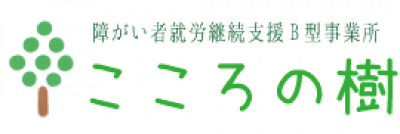初めての米作り
こんにちは、こころの樹です!
今回は先週もち米の稲刈りをしたので、田植えから収穫までの様子をお届けします!
こころの樹では、小麦や野菜の栽培をしていますが、今年度はお米の栽培にも挑戦しました。
お米は二種類、長野県オリジナル米「風さやか」ともち米を植えました。
田植えシーズンは地域差もありますが、4月下旬ゴールデンウィーク前後から始まります。
こころの樹の田植え日は5月24日でした。
私は以前から田植えをやってみたい!と思っていて、ようやく今年その念願が叶ったのでとても嬉しかったです。
田植えは2反の田んぼに、田植機を使って行いました。
田んぼに機械を入れたらすぐに田植えが始まるのかなと思っていましたが、まず田植機の植え付けの深さや株の間隔、植え付け速度などの調整を念入りに行っていました。
植え付けが深すぎると稲の初期生育が遅れる可能性があり、逆に浅すぎると水に流されて根が弱ったり、苗が浮いたりして、生育不良の原因になるので、しっかりと調整が必要だそうです。また株の間隔も一定間隔広げることで、株が取り込む光の量が多くなり丈夫な茎に育ち、病気にかかりにくくなる効果があるそうです。
調整が終わったら稲の苗を苗箱から苗とりボードという樹脂の板を使って出して、田植機の苗のせ台にセットしていくのですが、この作業がなかなか面白かったです。稲の苗はこんな感じになっています。
苗は12cmくらいで少しツンツンしていてかわいくて、とても癒されましたが、取り出してみると思っていたよりも根がしっかりと張っていて、苗の密度も高くてびっくりしました。
セットが完了したら田植え開始です!
田植機を運転していた代表も初めての田植え作業のようでした。初回はフィールドメジャー(巻尺)を畔の両端に伸ばして、それを目安にしながら運転していました。植え付けは機械が自動でやってくれます。
機械には二本の「植え付け爪」と呼ばれる爪がついていて、セットした苗をその爪で掻き取って、上から下に引き下ろして植え付ける、という仕組みになっているそうです。
近くで動いている様子を観察しましたが、本当にすごい発明品だと思いました。
いつから田植機はあるのか気になって少し調べてみたのですが、初めて特許が取得されたのは明治31年(1898年)だったそうです。その後硏究や開発が進んでいって、1960年代に入ってから人力田植機の実用化が始まったそうです。
作業中、私も一列だけ田植機を運転してみたのですが、左側のガイドをみながら視線を前方に切り替えてまっすぐ運転するのが難しかったです。タイヤも幅が狭くてハンドルで修正する感覚が車と違ったので運転するのが難しかったです。田植機を運転することにずっと憧れ続けていたので、嬉しさと感動、そして初めての緊張が交じり合って、心の中がけっこう忙しかったです。
個人的にはターンしてもう一列やってみたかったですが・・・来年に期待!
この日は途中から雨も降りだしましたが、本降りになる前に何とか作業を終えることができました。
数日後、機械で植えられなかった場所に苗を手植えしました。
左手に苗の束を持ち、右手で4,5本ずつとって親指と中指をうまく使いながら植えていきました。
田植え用の長靴をはいて作業していましたが、一歩進むたびに深く沈んでいくので、次の一歩を出すのが大変でした。バランス感覚がイマイチな私は作業よりも歩くことにかなり苦戦しました。
子供の頃に田植え経験があるという利用者さんも一緒だったのですが、とても慣れた様子でどんどん植えて進んでいく姿をみて、たくましいなと思いました。
この日私には水田にダイブしてみたいという欲求がありましたが、勇気がでませんでした・・・。
稲の苗は生長していくとイネ科植物特有の分けつ(元の茎の根元から新しい茎が次々と出てくる)という現象が起きて、一株あたりが大きくなるため苗の数よりも全体的な収穫量は増えるということを聞いたので、どうなっていくのか観察したいです。
こちらは田植えから2週間ほど経過した田んぼの様子です。
比較の写真が用意できなくて残念ですが、全体的にふわっとしていた様子からずいぶんたくましくなった気がします。
7月には、事業所のメンバー全員で草とりをしました。
無農薬栽培なので、雑草もとてものびやかに伸びて元気いっぱいでした。
手植えの時と同じく田んぼの中を一歩進むたびに沈んでいく感じでしたが、周りの利用者さんはそれぞれうまくバランスとりながら作業していたので、すごいなと思いました。私も体幹をもっと鍛えないといけないぞ!と改めて感じました。
稲と雑草との見分けが案外難しくて最初は戸惑いがありましたが、だんだん感覚で見分けがつくようになってきて、後半はかなりはかどった気がします。小雨の中での作業でしたが、一日頑張りました。
草とりから、さらに1ヶ月たった頃の様子です。
まだ稲穂のこうべは垂れていませんが、順調にすくすく育っています。
そして9月。そろそろ収穫が近づいてきました。
黄色く色づいている稲が、わかるでしょうか?これがもち米です。今回もち米は1反の1/3ほどですが、いよいよ収穫時期を迎えました。
その右側の稲は風さやかです。色づき始めてきましたが、収穫はもう少しあとです。
先週の木曜日・・・
待ちに待った稲刈り作業!お天気もよく最高の稲刈り日和でした。
時間がそれほどかからず、手刈りの方が収穫量も多くなるということで、収穫にコンバインは使わずに手刈りで収穫しました。この日も事業所のメンバー全員で取り組みました。稲刈りがはじめての利用者さんも多かったようです。
作業前に稲をみた時、固そうだったので鎌では刈りづらいのではないか?と思っていました。稲の根元を掴んでみると、植えた時は2,3本だった苗が直径4cmくらいに分けつして、手ごたえを感じましたが、スパッと切れて気持ち良かったです。
私が担当したところはもち米と風さやかの境界線でした。見た目が似ていて見分けがつくか心配でしたが、少し他の場所よりも間を開けて植えられていたので、そこに生えた雑草たちが目印になってくれました。時々時々立って位置を確認しながら作業を進めました。稲を掴んだときに田植えの日を思い出し、自然の力に大きさを感じ、感謝の気持ちでいっぱいになりました。
どんどん刈り進めていきます。
片手が稲の束でいっぱいになったら土手へ運びました。箱や箕(み)に入れて運んでいく人もいました。私は刈るのに夢中で運ぶのを後回しにしていましたが、気づいた人が土手まで運んでいってくれました。
運んだ稲はコンバインで脱穀しました。
稲を運ぶ人と、コンバインに稲を流していく人と分担をわけて作業を進めていく中で、それぞれ得意な分担を見つけて取り組んでいました。
はじめてだそうですが、なかなかの慣れた手つきでした!
私も今回はじめてコンバインを間近でみましたが、とてもカッコよくて、いつか運転してみたい気持ちが強くなりました。風さやかの収穫時にはコンバインを使うそうなので、稲の中を動いている姿を見るのが楽しみです。
利用者さんが収穫の喜びを表現してくれました・・・!
利用者さんに感想を聞いてみました!
すごく沢山のもち米が育っていました。 全て手刈りです。 他の利用者さん数名で協力してやりましたが、1人の担当範囲が幅1.5mくらいあったので橫幅が広く、低い体勢で動いて刈るのは大変でした。
鎌で稲の根っこを刈りました。 刈った稲は片手で4束まで持ち、手がいっぱいになったら近くの畔に置くと楽になりました。 鎌で怪我をしないように稲の掴み方に気をつけながらやりました。 左手は利き手じゃないので、掴みにくくて苦手だなと思いました。
雑草と稲の茎が似ていたので、間違えないように注意しました。 作業を続けて、稲が残り僅かになった時は嬉しかったです。 刈り終わると、次はコンバインに入れて、脱穀です。 利用者さんのKさん、Yさんに稲束を渡し、協力しながらやりました。 暑い中での一日作業で大変でしたが、最後まで刈り終えて良かったです。 また来年も稲を刈りをやりたいと思います。
職員さんからもコメントをいただきました!
私が稲刈りをするのは小学校以来なのでおよそ45年ぶりになります。
その久し振りの稲刈りは9月に入ったばかりのことでかなり暑かったですがそよ風が気持ちよかったです。
4人づつ東西に分かれ水田の中央に向かって刈りましたが、利用者の皆さんは大多数が稲刈りは初めてだというのに進行が速い。人生で2回目の稲刈り(大して変わらないか)の私は簡単に置いて行かれました。
観察するとある利用者さんは1列(各自4列を受け持った)だけを雑草を倒しながらあるところから手前に集中して刈り、稲も刈ったそばから横に置いておき、ある程度の量になってからまとめてコンバインのそばに持って行くという具合に稲を運ぶ時間を減らす工夫をしていました。
改めて利用者さんの作業に対する前向きな取り組み方に刺激を受けた1日でありました。
私も含め多くの利用者さんにとってはじめての作業でしたが、その時間を共有できて嬉しかったです。みんなで作業できてとても楽しかったです。
風さやかの収穫も始まるので、また楽しみです!米の違いについても(あるのかな?)観察してみたいと思います。
次回は、ちび畑の野菜出荷編です!
それでは近々またお会いしましょう!