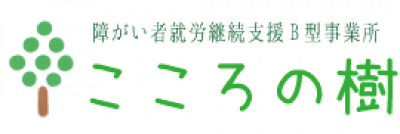ちび畑歳時記 I
ちび畑歳時記 I.種の話をします
種取りをしながら野菜作りを回す
皆んなでスイカを食べた後、種を残して貰ったことがありました。何で種が必要か?種代のお金をケチっているわけじゃありません(笑)
先シーズンも畑用に『カボチャ』『ズッキーニ』などの種取りをして、今シーズンはビニールハウス内で苗に仕立てました。
8月に人参の『黒田五寸』の種を頼まれて、買いに行ったのですが、どこを探してもF1種ばかりでした。
F1種の人参は長さも太さも粒ぞろいで、耐病性能も高く作りやすく売りやすいと言われています。
F1とは『雑種一代交配』といって、特定の種類を交配させて果実の大きさやきれいな粒ぞろいを得るもので、そこから採れた種を採取して蒔いても、次の世代に高品質な状態を引き継げない可能性が高い種なのです。
今のF1種は花は咲いても、種の実らないものもあります。
F1種はグローバル企業の手によって、世界規模で生産販売されていますが、『種』を独占されていることでもあります。
これでは種取りしながら、毎年の野菜作りを回していきたいと考えている者にとっては、次につなげることができなくなってしまいます。
地域性ということ
人間の場合、引っ越すと環境になれるのに時間が掛かることがありますが、植物も同じで土を含めたその農地の環境になじまないものがあります。
種が採れたということは、その土地に慣れたと言えるので土地に慣れた種をまけば、芽が出る確率が上がることが予想できます。
野菜や果物にも流行りすたりがあり、品種改良されてより美味しかったり収穫量が多い品種がいきわたると、それまで作られていた品種はだんだんと人気がなくなり種も手に入らなくなります。
『粟(あわ)』という穀物がありますが、今から60年くらい前には全国で200種くらいの品種がありました。
しかし米作の発展から粟の需要は少なくなり現在は4品種くらいまで減ってしまいました。
日本全国各地で米食の代わりに自分たちが食べるために、何世代も種取りを続けてその地方に適応した品種に分化しながら200種になったのでしょう。
言い換えるとこの品種の多様性は、その地域の文化であったと言えます。
長野県には『信州伝統野菜』とよぶ、地域独自の品種を認定したものがあります。
県では種子の流通まで含めて保護しています。
地産地消と言われますが、地域に根付いた野菜はその地域の環境に順応して育っているので、その地域で生活する者にとっては滋味あふれる食事をとれる可能性が高いと言えます。
循環する農業の一要素として、種取りを進めていきたいものです。
私たちの種採りのやり方
私たちは約600㎡ほどの畑で、ナス・シシトウ・ピーマン・オクラの他にカボチャ類の野菜を育てています。
その中でも比較的容易に種が採取できるのが、『カボチャとズッキーニ』です。
実がついてある程度の大きさになったところで、つるの部分にリボンなどを結んで印を付けます。
どちらの実も収穫時期を過ぎても可能な限り切り取らず、種の熟成を待ちます。
茎が枯れてきたら収穫し、雨のあたらない風通しの良い場所で保管し、種を取り出します。
取り出した種は直射日光を避け雨のあたらない風通しの良い場所でさらに乾燥させ、紙袋などに入れて保管します。
ゴーヤは実が熟すと黄変しパックリと口を開きます。
内側の鮮やかなレッドと外皮のイエローの対比がポップでナイスですが、『さわりたくナーイ』感じがモリモリなので、外皮が黄変したら収穫し種採り用の棚に収納します。
この方が圃場が汚れないのと、種の落下を防ぐことができるからです。
種の周りの赤いゼリー状の部分が乾燥したら、種を塊から個々に分けて保管します。
ネギはネギボウシを、ニラは花の終わった後の種袋が破裂し始めたころに収穫し、スーパー袋にためて口を閉じずに室内で乾燥させます。
乾燥が進んで種袋から種が自然に落ち始めたら、袋が空気で膨らんだ状態で口を閉めてガサガサ振り、種を分離させたら紙袋などに入れて保管します。
ピーマンとシシトウは、実の外皮が赤変して表面がしなびてきたら収穫し、雨のあたらない風通しの良い場所で保管します。この時に丸ごと干すのと二つに割って干す二つの方法があります。乾燥は二つ割りの方が速いですが、種からの芽吹きについてのデータは持ち合わせていません。
乾燥が進むと外皮から種が分離しやすくなるので、種を取り出したら紙袋などで保管します。
オクラは種取り用の目印を付けたら、茎についたまま実の外皮が枯れるのを待ちます。
外皮の枯れが進むと殻の縦方向にスリットが入ってくるので、これを見定めて種がこぼれない場所に横向きにおいて、追加乾燥します。
乾燥が完了すると、指で外皮をおさえただけで丸い種がコロコロと転がり出てきますので、これを集めて紙袋などで保管します。
食べるときのオクラの種は白色ですが完熟して乾燥させた種は黒色です。
スイカの種は、種取り用にカボチャと同様の方法でもかまいませんが、果肉が腐りやすいので美味しく食べているときにプッ吹き出して水洗い後乾燥させて保管が良いと思われます。
作物によってそれぞれに種取り方法がありますが、正統や元祖!といった方法は無いので、工夫を重ねて自分なりの最適を見つけていってください。
次回『ちび畑歳時記』は、『冬の土づくり』を予定しています。